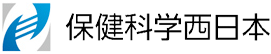INFORMATION 検査案内
保健科学西日本の検査に関する検査案内をお届けします。
DOWNLOAD ダウンロード

総合検査案内
総合検査案内をダウンロードしてPDF形式で閲覧していただけます。
圧縮されておりますので、お手数をおかけしますがダウンロード後に解凍してからご利用ください。
発行日:2019年4月作成 | 圧縮サイズ:61.4MB(ZIP) |解凍後サイズ:90.6MB(PDF)
※ アンチウイルスソフトウェアでスキャン済み
INFORMATION 検査案内
-
- 変更中止 2024.03.01 (金)
- No.2023-78 尿中総ヨウ素 一時受託中止
-
- 変更中止 2024.03.28 (木)
- No.2023-75 遊離βHCG (HCGβサブユニット) 受託中止
-
- 変更中止 2024.03.12 (火)
- No.2023-74 CKアイソザイム 一時受託中止
-
- 変更中止 2024.04.01 (月)
- No.2023-72 染色体検査 内容変更
-
- 変更中止 2024.03.01 (金)
- No.2023-71 レベチラセタム 内容変更
-
- 変更中止 2024.03.30 (土)
- No.2023-69 シアリル Tn 抗原(STN)他 内容変更
-
- 新規保険収載 2024.02.01 (木)
- No.2023-70 RAS遺伝子検査他 保険収載
-
- お知らせ 2024.02.14 (水)
- 西日本ラボラトリーにおける検査遅延
-
- 新規受託 2024.04.01 (月)
- No.2023-65 ムンプス〔HI〕 新規受託
-
- 変更中止 2024.03.30 (土)
- No.2023-64 エコーウイルス3型、7型、11型、12型 (HI 法)他 受託中止
-
- 新規保険収載 2024.01.01 (月)
- No.2023-66 プロスタグランジン E 主要代謝物ほか 保険収載
-
- 新規保険収載 2023.12.20 (水)
- No.2023-60 アミロイドβ42/40比(髄液)検査 保険収載
-
- 変更中止 2024.02.26 (月)
- No.2023-63 チミジンキナーゼ(TK)活性 受託中止
-
- 変更中止 2023.12.29 (金)
- No.2023-62 抗酸菌塗抹鏡検(直接塗抹法、チールネルゼン染色)受託中止
-
- 新規保険収載 2023.11.01 (水)
- No.2023-61 悪性腫瘍組織検査 保険収載
-
- 変更中止 2024.01.04 (木)
- No.2023-57 抗酸菌同定〔質量分析法〕 内容変更
-
- 変更中止 2024.03.30 (土)
- No.2023-56 TPA(組織ポリペプチド抗原)受託中止
-
- 変更中止 2023.11.01 (水)
- No.2023-54 インフルエンザA型、B型 内容変更
-
- 新規受託 2023.10.02 (月)
- No.2023-53 高感度 HBc 関連抗原定量 新規受託
-
- 変更中止 2023.09.01 (金)
- No.2023-52 B型肝炎ウイルスコア関連抗原(HBcrAg)受託中止
-
- 変更中止 2023.11.30 (木)
- No.2023-51 キニジン、アミカシン 内容変更
-
- 新規保険収載 2023.08.30 (水)
- No.2023-50 肺癌関連遺伝子多項目同時検査 保険収載
-
- 新規保険収載 2023.09.01 (金)
- No.2023-49 乳癌悪性度判定検査 保険収載
-
- 変更中止 2023.09.30 (土)
- No.2023-48 マンガン(Mn) 内容変更
-
- 変更中止 2024.03.30 (土)
- No.2023-47 ジョサマイシン(JM) 受託中止
-
- 新規保険収載 2023.08.01 (火)
- No.2023-46 A群β溶血連鎖球菌核酸検出 保険収載
-
- 新規受託 2023.08.14 (月)
- No.2023-44 ミエリン塩基性蛋白(MBP) 新規受託
-
- 変更中止 2023.08.01 (火)
- No.2023-43 ミエリンベーシック蛋白(MBP)受託中止
-
- 新規受託 2023.07.10 (月)
- No.2023-42 遊離β HCG(HCGβサブユニット) 新規受託
-
- 変更中止 2023.07.01 (土)
- No.2023-41 遊離β HCG(HCGβサブユニット) 受託中止
-
- 変更中止 2023.09.30 (土)
- No.2023-38 アルドステロン/レニン活性比他 受託中止
-
- 変更中止 2023.10.02 (月)
- No.2023-37 NTx(Ⅰ型コラーゲン架橋N-テロペプチド) 内容変更
-
- 変更中止 2023.07.31 (月)
- No.2023-33 NTx(Ⅰ型コラーゲン架橋N-テロペプチド)(血清) 受託中止
-
- 変更中止 2023.06.01 (木)
- No.2023-30 CK-MB 内容変更
-
- 変更中止 2023.06.01 (木)
- No.2023-29 ミオグロビン定量 内容変更
-
- 変更中止 2023.05.31 (水)
- No.2023-28 PSA-ACT 受託中止
-
- 変更中止 2023.03.31 (金)
- No.2023-19 薬剤感受性検査(実施薬剤) スペクチノマイシン(SPCM) 受託中止